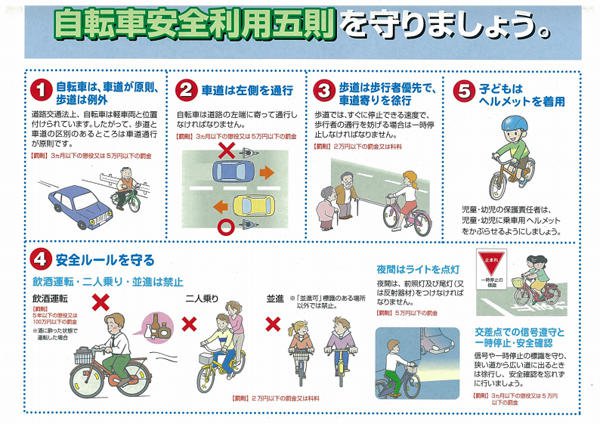クルマが1台分しか入れない一方通行路を走っていたら、我が物顔で、こちらのクルマに向かって来る自転車とぶつかりそうになった……。片側1車線の相互交通路の一般道を走っていたら、左側の路側帯を前から自転車が逆走してきた……。
クルマの運転者だったら、一度は「自転車は車両、逆走は違反じゃないのか?」と憤りを覚えたことがあるはずだ。
そこで、自転車の逆走について、法律ではどうなっているのか? モータージャーナリストの高根英幸氏が解説する。
自転車講習を受ける人がかなりの勢いで急増中!
この10年ほどで、都市部の道路では自転車が走る割合が増えた。ロードバイクブームや健康ブーム、東日本大震災など災害によって交通網が寸断されたことから、自分の自由になるエコな移動手段として自転車が見直されたこともあって、自転車の利用台数は増えている。都心ではシェアサイクルも普及し始め、着実に移動手段の選択肢として浸透してきている印象だ。
しかも自転車が関係する交通事故自体は減少している。特に自転車事故の8割を占めるクルマとの衝突事故は、この10年でほぼ半減しているのだ。
しかしながら、都市部の道路状況を見てみると自転車運転者による危険な走行は、減っているようには感じない。これは筆者の主観によるものだけではなさそうだ。
2015年6月から、自転車を運転して危険行為による取り締まりを3年以内に2度受けたり、交通事故を起こすと、自転車運転者講習を受けることが義務付けられている。
警察庁広報室に確認したところ、この自転車運転者講習、2015年は6月からということもあって受講者数は7人だったが、翌2016年は80人、2017年は122人、2018年296人とかなりの勢いで増えているのだ。2019年も8月末までで195人と昨年同等のペースで進んでいる。
検挙されるまでもない軽微な違反はそれ以上に膨大であるから、車道と歩道を走る自転車の無法ぶりが目立つのである。なぜ、こんな状態になってしまったのだろう。
中途半端な周知により、完全な交通ルール統制でないことが原因
自転車の交通ルールがPRされるようになって「自転車は原則車道を走ること」は、子供から高齢者まで知られるようになって守られているようにみえる。だが、そのほかの交通ルールは意外と覚えていない自転車運転者が多いようだ。
無灯火、車道(路側帯も含む)の右側通行、スマホ操作や両耳イヤホンで音楽を聴きながらの走行といった、歩行者感覚の自転車運転者は相変わらず多い。
それでも以前は歩道を走っていたから、歩行者にさえ気を付ければよかったが、車道に出てくるようになって、ドライバーの方が気を付けなくてはいけない状態になってしまったのだ。
小学生と70歳以上の高齢者は歩道を走ってもよい、ということになっているが、「走ってもよい」という表現だから判断が難しいのか、結局フラフラと車道を走っているケースが多い。
そのほか、全年齢の自転車運転者でも、危険な状態だと判断できた場合は車道ではなく歩道を走ることが認められているし、自転車通行可の標識がある歩道は自転車も普通に走ってよい(ただし歩行者が優先)のに、そんな標識を確認することもなく、頑なに車道を走っている自転車運転者も多い。
旧一級国道(数字2ケタまでの国道)でもビュンビュンとクルマが走る片側2車線の路肩を、ママチャリやクロスバイクでヘルメットを被らずに走るような人たちも珍しくない。
危険だと感じてはいても、頑なに法律を守ろうと思っている(それも間違った知識で)人も多いのだろう。ドライバーとしては、すれ違う時、追い越す時にヒヤヒヤする思いをしているのではないだろうか。
一方で警察官でも従来通りに自転車で歩道を走っているケースも多く見かける。いかに自転車に乗ることの責任感が希薄か、ということを表している光景だ。
自転車の逆走は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金!!
2013年12月1日より、道路交通法が改正され、自転車の通行可能な場所が変更、逆走が禁止になった。
それまでも当然逆走はNGだったのだが、歩道がない道路にある路側帯(一本線で車道と区分された歩行者や自転車の通行スペース)では、双方向に通行できた。 しかし、2013年12月1日から、路側帯を走る場合も道路の左側部分に限られることになった。
【改正前】自転車が通行可能な路側帯は、双方向に通行可
【改正後】自転車が通行可能な路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯のみ通行可
自転車が通行可能な路側帯というのは、白線1本で車道と区切られたエリアのことだ。2本で区切られたものは歩行者専用である。
道路の左側部分(自転車から見て進行方向左側部分)を通行するルールによれば、自動車の前方左手から当該自動車に向かって道路を逆走してくる自転車は、道路の右側部分(道路の右側の路側帯)を通行していることになる。
つまり、道交法の通行区分違反となり、逆走自転車の運転者には「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科されるのだ(119条1項2号の2)。
一方通行の標識は「自転車を除く」という補助標識がなければ逆走は違反!
意外と知られていないのが一方通行の規制だ。「自転車は除く」といった補助標識が追加されていなければ、逆走は違反だ。しかし、この補助標識が付いていない一方通行路も意外と多いのである。
警察庁広報室によれば、一方通行の交通規制は交差点での整流や単純化のため、あるいは相互通行では幅員が足りず、安全と円滑な交通を確保する必要がある場合に実施しているそうだ。
筆者の住んでいる近所の一方通行路で、クルマが前から来ても我が物顔で逆走自転車がいかに多いことか。一方通行の標識はおろか、自転車を除くという補助標識を理解している人がどれくらいいるだろうかと、いつも思っている。
自転車も守るべき一方通行を逆走したからといって、すぐに取り締まりにあうことはなさそうだが(実際に見たこともない)、交通事故は起こさなくても周囲の交通や歩行者に危険をおよぼしたり、警察官の指導警告に従わない場合は検挙される可能性はある。
自転車が危険な原因の根本は、自転車も車両なのだが、未だに歩行者気分で自転車を運転している人が、あまりにも多いということにあるのだ。
自転車運転者の無謀な運転で交通事故が起こった場合、自転車運転者にも重い責任が課せられるケースも増えてきた。
逆走自転車とクルマが事故を起こした場合はどうなる?
気になるのは逆走自転車とクルマが事故を起こした場合には、自転車側の過失も認められるのかということ。
知り合いの自動車保険屋さんに聞いてみたが、逆走自転車とクルマとの対向車同士の事故の場合、自転車はクルマと比べて交通上弱い立場にはあるものの、逆走自転車側に2程度(事故状況によっては自転車側に重過失ありとして、4割程度)の過失割合が認められるケースが多いという。
クルマのドライバーは納得いかないかもしれない。しかし、それはドライバーが免許を取得していることで交通法規を熟知しており、さらにクルマという機械を操ることで周囲に危険を及ぼす可能性を予見できていると見なされるからだ。
つまり、よほど自転車側に明確な責任がない限り、クルマのドライバーの方が事故の責任が重くなる。
だから、道路を走る自転車を邪魔だと思うのは、ドライバーの「傲慢」だと思った方がいい。
それくらい、クルマを運転するという行為には責任が課せられているのを我々ドライバーは常に忘れないようにしなければいけないのだ。
相互通行路でも逆走が危険な理由
「後方からクルマが迫ってくるより、対向車として向かってくる方が見えるので安心する」という理由で、クルマの進行方向と逆に走行してくる(右側通行)自転車運転者もいるようだ。
しかし、これは交通ルールに反しているだけでなく、危険な行為なので、絶対に止めていただきたい。
もし読者諸兄の回りで「自転車は車道ならどちら側を走ってもいい」あるいは前述のように「右側通行の方が安心する」と右側通行している人がいたら、その危険性を説明して、改めるように勧めてほしい。
自転車で走行していて、左端に停車中のクルマがいた場合、それを避けるために右方向に進路を変えて車線の中央付近を走ることになるだろう。
この場合、自転車が左側通行していれば後方を走るドライバーは、右側に進路を変更してくる自転車の動きは見える。
しかしドライバーから見て左側を逆走してくる「右側走行」している自転車は、停車中のクルマの影から突然、自転車が出現することになる。これがどれだけ危険であるかは、説明するまでもないだろう。
そのほか、道路を横切ったり、駐車場などから道路へ出ようとするクルマは、左右から来るクルマに注意しながら発進させるが、手前側の左車線は当然、右方向からくるクルマやバイク、自転車に注意してクルマを発進させる。
特に左折して走行車線に合流する場合、左側の対抗車線はクルマなどが来ていないか一瞬確認するだけのドライバーも多いだろう。そこに手前の車線に左から自転車が進んでくるとは想定していないハズだ。
先が左にカーブしていたりして見通せなければ、直前まで自転車の存在には気付かない場合もある。そんな状態で衝突事故を起こしてしまったら、右側通行してきた自転車運転者も当然、事故の責任は問われることになるのだ。
記事元:ベストカー